・3歳の頃に幼稚園で発達遅れの指摘を受ける。
・幼稚園に通いながら、週4-5で療育に駆け回る。
・小学校は通常級を選択。週2時間の通級利用。
・中学校からは特別支援学級を選択。現在楽しく通っている。
・知能検査の数値は徐々に下がってきており、現在は境界知能。
・言語理解が極端に凹。そのため学習面が厳しい。
・中学の部活は運動部に入部。
・好きなもの:野球・鉄道・ディズニー・ショーなど含む音楽
3歳「姿勢が続かない」「すぐ疲れる」…気になっていた発達の遅れと体幹の弱さ
現在(2025.7)中学1年生になる長男には発達障害の特性があり、3歳のころから「体幹の弱さ」が気になっていました。
椅子に座っていてもすぐにグニャっとなったり、走ってもフラフラしていたり…不安になる毎日でした。
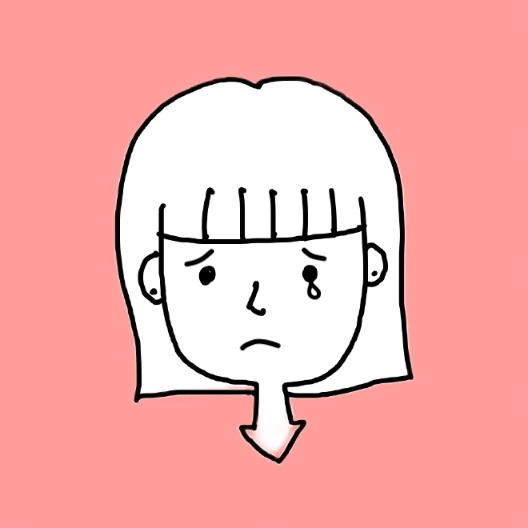
まだ幼児期のお子さんをお持ちの親御さんは、同じような不安を感じていらっしゃる方も多いんじゃないかな。
当時はなんとか長男の発達に良いものを!!
という気持ちで出来ることになんでも取り組む毎日。
あの時の自分に声をかけてあげられるのであれば、
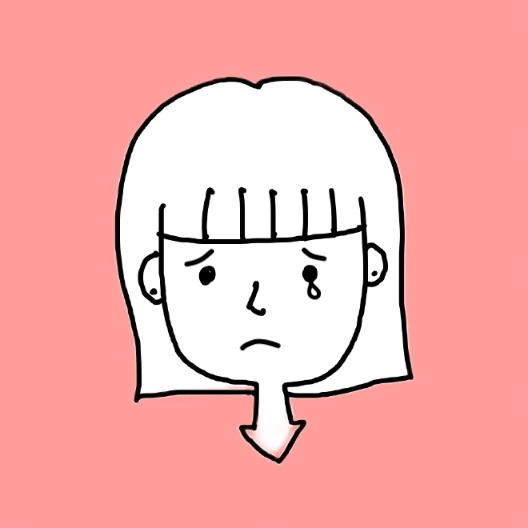
「もう少し肩の力を抜いて!」
と言ってあげたいけれど、「あの時の時間があったからこそ今の長男がいる」という気持ちがあるのも確かなのです^^
成長につれて発達特性は残っており(むしろ濃くなってるかも?笑)、中学からは特別支援学級に通っている長男ですが、運動部で部活に励んでいます。
そこで、家庭で楽しくできる「遊び」こそが体幹の支えになる、というモットーのもと、小さい頃に少しずつ続けていた体幹トレーニングの記録をまとめました。
何か少しでも参考になれば幸いです。
発達障害と体幹の関係って?|我が家が感じた“弱さ”の正体
私は専門家ではありませんが、療育の先生から
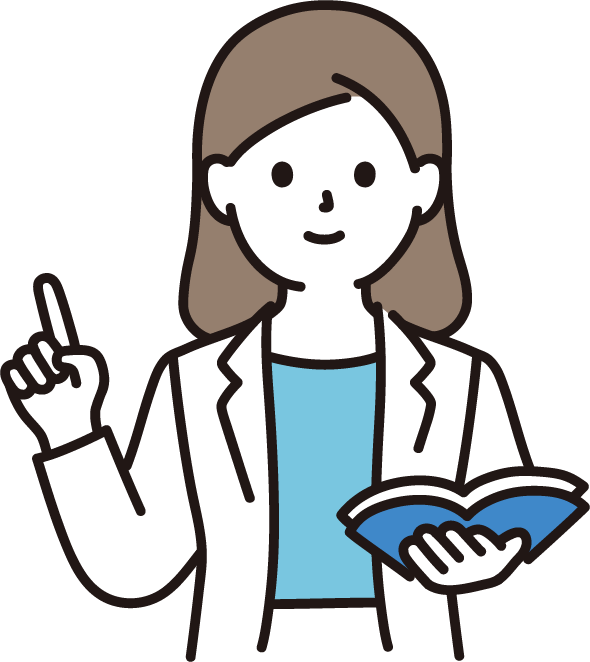
「体幹が弱いと、姿勢が崩れやすく集中もしづらくなることがある」
と教えてもらいました。
実際、長男は3歳の頃、座っていると姿勢を保つのが難しかったり、走るとすぐに転んだりして、日常生活の中で「なんとなく体の軸が不安定だな」と感じることが多かったです。
幼稚園の先生からは「しゃがんで砂場遊びができない」ことを指摘されました。
言われた時はよくわからなかったのですが、体幹が弱いとしゃがんだ時に体を支えられず尻もちをついてしまうんですね。
娘が同じくらいの年齢の時に普通にしゃがんで遊んでいるのを見て
「先生が言っていたことはこういうことだったのか〜」と衝撃を受けたものです。
詳しいことは、例えば本などでも専門的に紹介されていますので、興味がある方は参考にしてみてください。
👉 📕「
家庭でできる体幹を鍛える遊び・トレーニング5選【3・4・5歳向け】
発達障害のある長男が3〜5歳の頃、体幹を鍛えられる遊びをいろいろ試してきました。
遊びを“トレーニング”にしすぎず、「楽しく・気づいたら鍛えられている」ことを意識して、家庭や近くの公園で取り組めるものを紹介します。
① トランポリン
長男に「発達の遅れがあるかも」と知った時、まず初めに藁にもすがる思いで用意したのがトランポリンでした。
療育先でもトランポリンはよく使用されていて、先生からも「感覚統合の面でも良い」と聞いていたので迷わず購入。
今年に入ってから手放したのですが、長男だけでなく、長女や次男、それからお友達もぴょんぴょん跳んでくれて、なんと9年もの間、使用することができました。
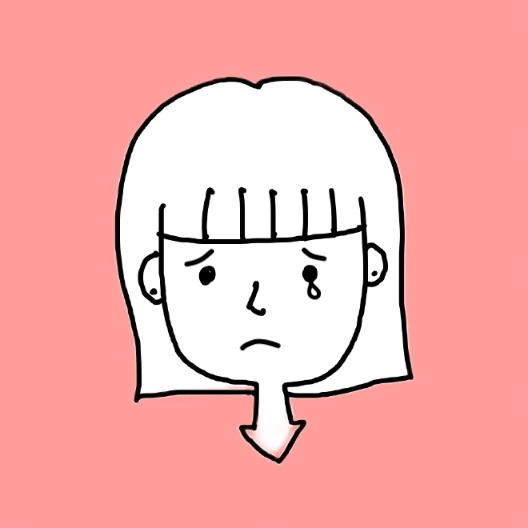
手放すときは正直グッと込み上げてくるものがありました。
小さな家庭用トランポリンは体幹トレーニングにぴったり。
跳ねるたびにバランスを取ろうとするので、自然とお腹・背中に力が入ります。
これが体幹を鍛えることに繋がるんだとか。
「せっかく買ったのに使わなくなってしまった」なんてことは避けたいですよね。
そこで、我が家でトランポリンを習慣化させたポイントをお伝えします。
・出しっぱなしにしておくこと
・テレビなど別のことも一緒にできる場所に置いておくこと
・決して強制はせず、跳びたい時に跳べる状況を作っておくこと
・同時にキャッチボールをしてみたり、タンバリンを叩いてみたり、いつもと違うことを混ぜていくと飽きずに楽しめます
家庭用のトランポリンなので折りたたみはもちろんできるのですが、折りたたんでしまうと出すのが億劫になってそのうち使わなくなっていくので要注意です!
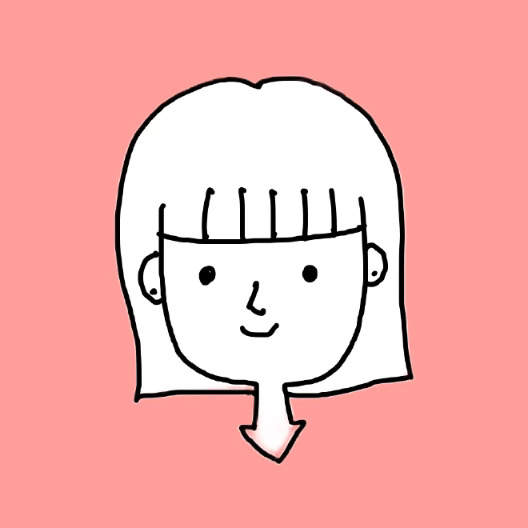
防音のためのマットは、ストレッチで使ったり鉄棒で使ったり、トランポリン以外でも使用できるので購入する際は必ず一緒に購入することをおすすめします!
② 動物歩き(クマ・カエルなど)
「クマ歩き」「カエルジャンプ」など、動物のまねっこをする遊びです。
これも幼稚園の運動の先生から「お母さんとお父さんが一緒になってやってください」とアドバイスをいただいて始めました。
家で親も一緒にやると笑いながらできて、運動が苦手でも続けられたのはよかったと思います。
このあたりが上手にできるようになったあとは、そのままの流れで「雑巾掛け」にシフトして行きました。

雑巾掛けは競争もできるので◎
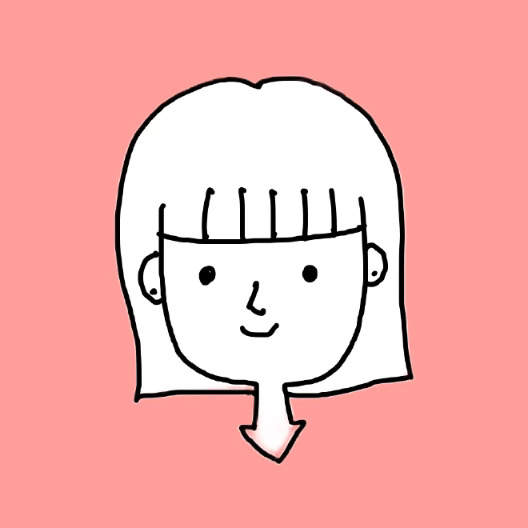
何よりも家が綺麗になるので、親としては「どんどんやれー!」の気持ちでしたね(笑)。
③ マンションと家の階段上り下り
幼稚園の先生から、「手すりを使わずに両足を交互に出して階段を上手に降りることができない」との指摘を受け、これも体幹に関わる部分と知ったので毎日のルーチンに取り入れました。
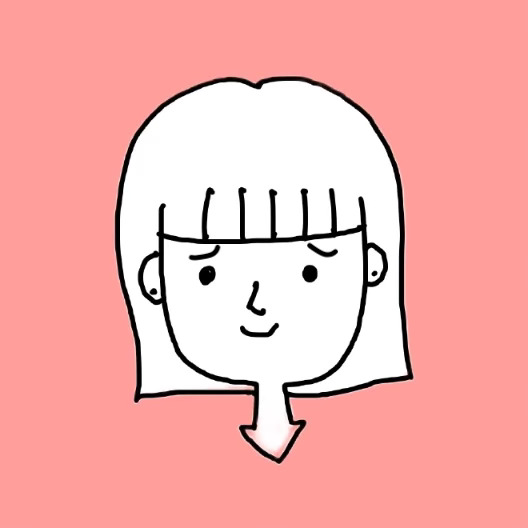
体幹が弱いと、特に階段を降りるのが不安定になるんですよね。
当時、マンションの6階に住んでいたため幼稚園の行き帰りはエレベーターを使わず、階段を使用するようにしました。
でも、エレベーターを使わずに1〜2階分だけ階段を一緒に昇り降りするだけでも十分。
最初は「手すりを持ってゆっくり」でOKです。
毎日、コツコツ続けることが大事だと思います。
一方、ちょっと大変だったのは、急いでいる時でもエレベーターに乗ってくれない時期があったことです。
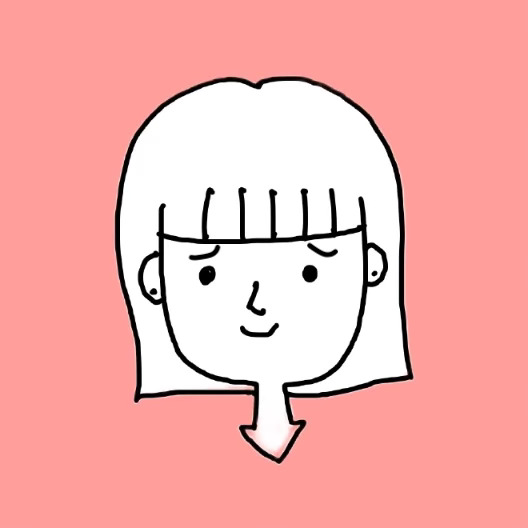
成長と共に言語理解が進んで途中からそのようなことはなくなりましたが、急いでいる中、癇癪を起こす長男に何度もイライラしたし、何度も一緒に泣きました。
④ 縄跳び
幼稚園の運動会で縄跳び種目があることがわかり、練習開始。
幼稚園で使用する縄跳びと全く同じものを家でも購入して練習をしました。
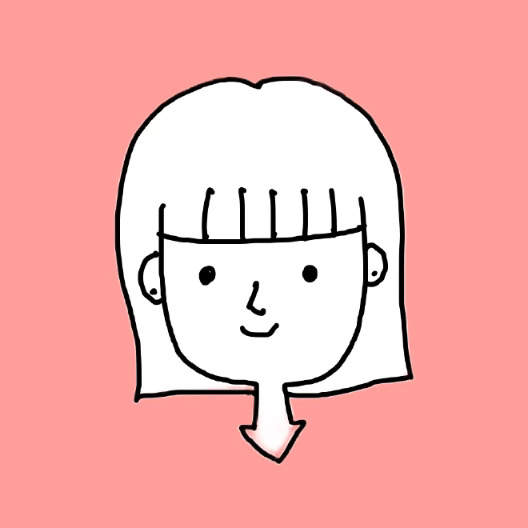
発達障害がある子には、長男のように緊張感が強いタイプだったり、不器用なタイプの子も多いです。そのような子たちは、なるべく同じものを家でも用意してあげると安心して取り組めますよ^^
最初のうちはニョロニョロヘビや郵便屋さんから始めて、次は私たち親が縄を回して跳ぶ練習をしました。
縄跳びに関しては体幹だけでなく手足をリズムよく同時に動かすという面で、とてもハードルが高かったりします。
ですが、これも本当にコツコツと「ジャンプだけ」「縄を回すだけ」など少しずつ少しずつ練習を重ねていって跳べるようになりました。
※DCD(発達性協調運動障害)があるお子さんだと縄跳びはとても辛い運動になってしまうかもしれません。その辺りは、お子さんの様子を見ながら楽しめる範囲で進めてくださいね。
縄跳びは100均に売っているようなものだと軽すぎて逆に難しくなります。
そのため、最初は多少重みがあって安定感のある縄跳びがおすすめです。
⑤ 鉄棒

トランポリンに続き、家にお出迎えしたのが鉄棒でした。
ぶら下がるだけでも十分に握力と体幹の両方が育ちます。
「1秒チャレンジ」から始めて、いつの間にか「5秒!」「10秒!」と本人も楽しそうに挑戦していました。
また、幼稚園では鉄棒に力を入れていたので、家で好きなだけ練習をさせてあげたかったというのもあります。
練習を重ねた結果、気が付けば逆上がりもできるように。
長男は体の使い方が不器用で、必要な箇所に力を入れられていないように見えることが多かったのですが、鉄棒は「今、腕のどこに力を入れるべきか」という筋肉の使い方の練習にもなっているようでした。
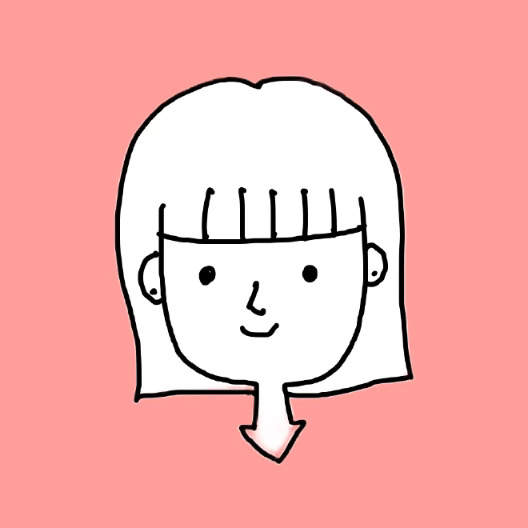
公園にも鉄棒はあるので、見かけたらやってみる、でも十分だと思います^^
家庭での体幹トレーニングで気をつけたいこと
- 無理させないこと:嫌がるときは無理せず、今日はおやすみに。
- 成功体験を重ねること:「昨日より2秒長くできたね!」など、達成感を伝える。
- 安全第一:マットを敷いたり、家具の近くを避けて遊ぶ。
トレーニングというよりも、「親子の遊び」として取り組むのが長続きのコツです。
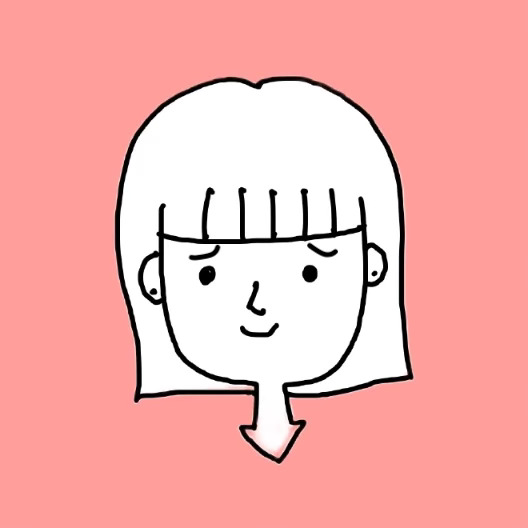
私自身、当初は気持ちばかりが焦ってしまって、毎週末大きな公園につれていき、まだ出来もしないアスレチックに挑戦させたり、怖がる遊具に挑戦させり…なんてこともありました。
「家でできることをしよう」と決めてからは、私も気が楽になったし、長男も楽しそうに取り組んでくれました^^
長く続けていったことで、少しずつ、座る姿勢が安定したり、転びにくくなったり、本人の中でも「動くって楽しい」と思えるようになったのかもしれません。
そして何より、「親子で一緒に楽しんだ時間」が、彼の自信につながったと感じています。
まとめ|発達障害の子に向けた体幹トレーニングは焦らず、楽しみながらできることを
長男は中学生になり、体幹の弱さもずいぶん改善されてきました。
今でも発達の特性はあり運動神経も決して良いとは言えませんが、体を動かすことが大好きになり、中学校では運動系の部活に所属して楽しそうに活動しています。
幼稚園の頃は、かけっこでいつもビリ。
走るのも嫌がっていた息子が、小学校高学年になると1位や2位でゴールするように。
順位が全てではありませんが、そんな姿を見せてくれたとき、「ああ、あの頃の小さな積み重ねが今につながっていたんだな」と心から思いました。
もちろん、いますぐ劇的に何かが変わるわけではないし、特性のあらわれ方もお子さん一人ひとり違うので、何かを“保証”することはできません。
でも――
親子で向き合って、コツコツ積み重ねていくことで、少しずつ“変わっていくこと”がある。
このことは、私自身が一番強く感じていることです。
同じように「体幹が弱いかも」と感じている親御さんへ。
大丈夫、焦らず、楽しみながら。今できることを、できる範囲で。
一歩ずつ進んでいけば、きっとその先に見えてくるものがあります。
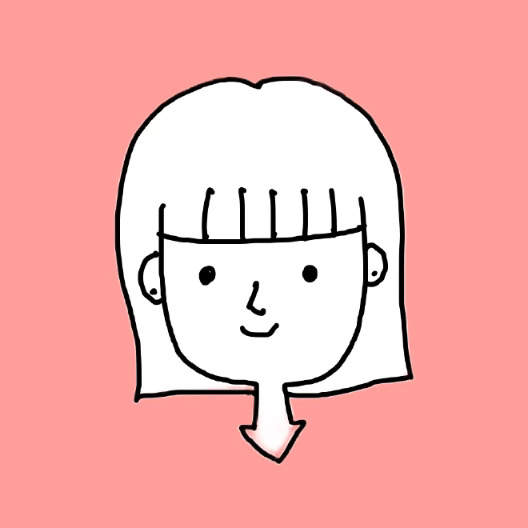
私たち親子の経験が、何か少しでも参考になれば幸いです。
参考|発達障害児向け 体幹トレーニンググッズ
⭐️トランポリン
一緒に購入がおすすめ!👉 トランポリンのマットをAmazonで見る
⭐️縄跳び
⭐️鉄棒






コメント